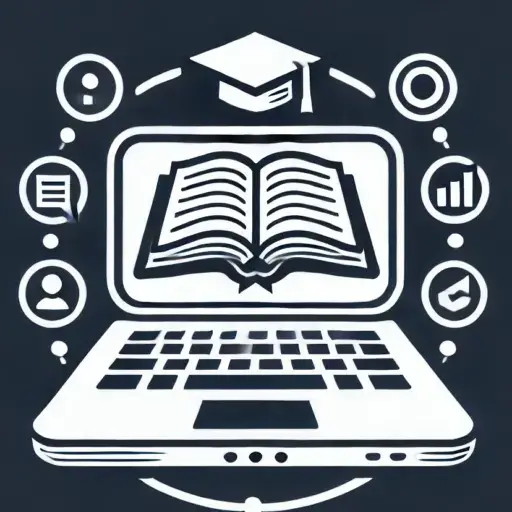投資初心者から中級者まで、多くの人が関心を持つ「株式・債券・先物」。中でも株式投資は最もポピュラーな手段の一つですが、リターンの大きさと同時にリスクも内包しています。今回のUR-U講義では、株式投資におけるリスク分散手法や、上昇しやすい株価の見極め方、投資スタイルの選び方について、具体例を交えながらわかりやすく解説されていました。
この記事では、講義内容の重要ポイントをまとめつつ、初心者にもわかりやすく実践に活かせる情報を丁寧にお伝えします。
株式投資の基本とトレードスタイルの違い
株式投資には、長期・中期・短期という3つのトレードスタイルがあります。それぞれの違いやメリット・デメリットを理解することで、自分に合った投資方法が見えてきます。
長期・中期・短期トレードの違いとは?
講義の中では、株式投資のスタイルとして以下の3つが紹介されていました。
- 短期トレード(デイトレード):数秒〜数日のスパンで売買を行う
- 中期トレード:1週間〜数ヶ月のスパンで保有
- 長期トレード:1年〜数年単位で保有し、資産形成を狙う
たとえば、短期トレードでは株価チャートに張り付き、わずかな値動きで利益を得ようとしますが、そのためには高度なスキルと精神的余裕が必要です。反対に、長期トレードでは企業の財務状況や将来性を分析し、じっくりと投資するスタイルとなります。
講義でも竹花氏は「自分は中長期投資が基本である」と語っており、企業のPLやキャッシュフロー、IR情報、チャート分析など、複数の視点から総合的に判断する力が重要だと強調していました。
したがって、自分のライフスタイルや性格に応じて、どのスタイルを選ぶべきかを考えることが第一歩となります。
短期トレードの落とし穴とリスク
短期トレードは一見「すぐに稼げそう」というイメージを持ちがちですが、実際には非常に高度なテクニックと、冷静な判断力が求められます。
たとえば、ある銘柄を買った瞬間に数秒で価格が下落した場合、瞬時の判断で損切りができなければ、大きな損失につながることもあります。竹花氏も「画面に張り付いて10秒の値動きに一喜一憂する生活は、自分にとって幸せではない」と語っており、感情に左右されやすい人には短期トレードは向かないとしています。
また、短期売買では売買回数が増えることで手数料がかさみ、結果的にパフォーマンスが悪化するケースもあります。したがって、「短期=稼げる」ではなく、自分の資産管理や精神的安定を最優先に考える必要があるのです。
中長期投資で重要な企業分析とチャートの見方
一方、中期・長期トレードでは、「今この企業の株を買って、1年後にどうなっているか」を冷静に判断することが求められます。ここで重要なのが、財務指標・キャッシュフロー・チャートなどを用いた企業分析です。
講義では「未来の株価は誰にも予測できないが、企業の成長性や市場環境から中長期的なトレンドを読むことは可能」と解説されていました。実際に、IR情報や決算資料、業界動向などを継続的にチェックすることが、成功する投資家の共通点だと言えます。
では、リスク管理の具体的な方法について見ていきましょう。
投資におけるリスクとリスク分散の考え方
株式投資においては、必ずリスクが存在します。価格は上がることもあれば下がることもあり、それを予測することは困難です。したがって、リスクを分散する投資手法を理解することが非常に重要です。
株式投資は「常にリスクがある」ことを理解する
たとえば、1万円で購入した株が1万2000円に上がれば利益が出ますが、8000円に下がれば損失です。売らなければ含み損であっても、心理的なストレスは避けられません。
このようなリスクを回避するために、価格に一喜一憂せず、長期目線でコツコツと投資を続ける仕組みが求められます。ここで登場するのが「ドルコスト平均法」です。
ドルコスト平均法と定額・定量購入法の違い
ドルコスト平均法とは、毎月決まった額(例:1万円)を一定間隔で投資する方法です。株価が高いときは少し、安いときは多く買えるため、結果として平均取得単価を下げる効果があります。

上図のように、価格変動がある中で毎月1万円を投資すると、高いときには少ない株数、安いときには多くの株数を買うことになります。その結果、購入単価が平均化されていくのです。
一方、定量購入法(毎月100株など)では、株価が高騰していても同じ株数を買うため、高値づかみのリスクが高くなります。
バリュー平均法という新しい投資アプローチ
竹花氏が推奨していたのが、ドルコスト平均法よりもさらにリスク分散に優れた「バリュー平均法」です。
これは、資産額が毎月一定金額に達するように投資額を調整する方法です。たとえば、2ヶ月目に資産が想定以下であれば追加投資を行い、想定以上なら売却するという形で、ポートフォリオ全体のバランスを保つことができます。
この手法は手間はかかりますが、「投資資産に目標を持たせて管理する」という意味で非常に合理的で、感情に左右されにくいメリットがあります。
株価が上昇しやすい2つのタイミングとは
投資家として「いつ買うべきか」は永遠のテーマです。講義では、株価が上がりやすい2つの明確なタイミングについて解説がありました。
株式分割が株価に与える影響とは?
株式分割とは、1株の価格を下げて、保有株数を増やす仕組みのことです。たとえば、1株10万円の株を2分割すると、1株5万円の株が2株に増えることになります。
株価自体の価値は変わりませんが、価格が下がることで個人投資家が買いやすくなるため、結果的に株価が上昇しやすくなります。
実際に株式分割を発表した企業は、その後の取引量や株価上昇率が高くなる傾向があります。したがって、株式分割の発表は要チェックです。
IPO(新規上場)銘柄はなぜ上がりやすいのか?
IPO(新規上場)とは、未上場企業が証券市場に株式を公開することです。上場直後のIPO株は、以下の理由から高確率で株価が上昇する傾向にあります。
- 初値が控えめに設定されやすい
- 市場での注目度が高く、需給バランスが買いに偏る
- 個人投資家の期待値が高まる
ただし、IPO株を購入するには、証券会社の抽選に当選する必要があるため、主幹事証券会社の口座を事前に作っておくことが重要です。
まとめ:講義を通して得た投資の本質
今回のUR-U講義を通じて、株式投資には「正しい知識」と「感情に左右されない冷静な判断力」が不可欠であることがよくわかりました。
特に以下の3つのポイントは、今後の投資において強力な指針となるでしょう。
- 中長期的な視点で企業を分析する
- リスクを分散する投資手法(ドルコスト・バリュー平均法)を使う
- IPOや株式分割といったタイミングを見極める
ちなみに私自身も、過去にバリュー平均法をExcelで手計算しながら運用した経験があります。少々手間はかかりましたが、「今月は買うべきか?売るべきか?」という判断が明確になり、感情に流されることがなくなりました。
株式投資は一朝一夕で結果が出るものではありません。ですが、こうした「仕組み」と「判断軸」を持つことで、長期的に安定した成果を目指せるようになります。