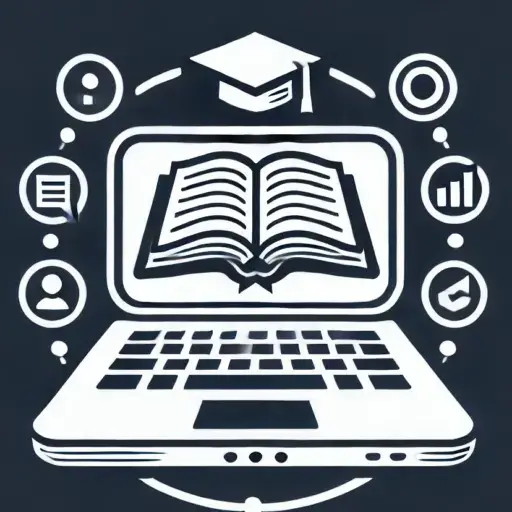今回竹花貴騎氏のUR-Uで学んだことは「これからの社会で訪れる格差社会の拡大」について。このテーマは、これからの5〜10年で私たち全員が直面するかもしれない社会の変化と、その原因についてです。以下、とてもわかりやすいので是非視聴してみて下さい。今回はなぜお金持ちが国外逃亡するのか?こちらについてまとめていきます。
なぜ企業は黒字でもリストラを進めるのか?
「企業が黒字にもかかわらずリストラを行う理由」について解説がありました。その背後には、株主の利益を最大化するという明確な目的があります。授業では次のポイントが説明されていました。
- 株主の利益追求
株主は利益を最優先に考えるため、企業は効率化のためにリストラを進めます。リストラにより、人件費が削減され、株主が得られる利益が大幅に増加するからです。 - AIやロボット技術の進化
企業は、人件費を削減するためにAIやロボットを積極的に導入しています。これにより、人間の労働が不要になる職種が増えているのが現状です。
今後の選択肢:低賃金労働かリストラか
この動画の中で「この先の社会では、多くの人が次の2つの選択肢を迫られることになる」との指摘がありました。
- 超低賃金で働く
これからの社会では、安定した高賃金の仕事はますます少なくなり、多くの人が低賃金で働くことを余儀なくされる可能性がある。 - 職を失う(リストラ)
AIやロボットに取って代わられることで、現在存在している多くの仕事が消滅する可能性がある。
ベルカーブ時代からロングテール時代への移行
現代社会では、かつての「ベルカーブ時代」から「ロングテール時代」へと移行が進んでいます。それぞれの時代は、社会構造や人々の生活に大きな影響を与えてきました。
ベルカーブ時代とは、所得や生活水準が正規分布に近い形で、中間層が社会の中心に位置していた時代です。多くの人が安定した生活を送り、家族や地域社会が密接なつながりを持っていました。この時代は以下のような特徴があります:
- 中間層が購買力の主役となり、経済を支えた。
- 大衆向けの商品やサービスが市場の主流。
- 安定した雇用が保証され、終身雇用制度が広く浸透していた。
ロングテール時代の特徴
一方、ロングテール時代では、技術革新やグローバル化の影響で社会の構造が大きく変わりました。以下のような特徴が顕著です:
- 所得が二極化し、少数の高所得者と多数の低所得者が形成。
- ニッチ市場の拡大によって、多様な消費行動が生まれる。
- 自動化やAIにより、専門的なスキルが求められる社会。
両時代の比較
| 項目 | ベルカーブ時代 | ロングテール時代 |
|---|---|---|
| 所得分布 | 中間層が中心で、正規分布に近い形。 | 高所得者と低所得者に分極化。 |
| 経済の安定性 | 中間層の消費によって経済が安定。 | 格差拡大により社会全体の安定性が低下。 |
| 消費行動 | 大衆向け商品が中心で、均一化された消費が主流。 | ニッチ市場が拡大し、消費の多様化が進む。 |
| 働き方 | 終身雇用が一般的で、職業を通じた安定した生活。 | AIや技術革新により、高度なスキルが求められる。 |
| 市場の特徴 | 大衆向けの商品・サービスが主流。 | 特定のニーズに応えるニッチ市場が急成長。 |
時代の転換と私たちへの影響
この移行は、単に経済構造が変わるだけでなく、人々の生活スタイルや働き方にも影響を及ぼしています。ベルカーブ時代には多くの人が同じ価値観や目標を共有していましたが、ロングテール時代では「多様性」が尊重される一方、格差や不平等の拡大が課題となっています。
もう一つ重要なテーマとして、「税金が格差拡大に与える影響」について解説がありました。
- 累進課税の仕組み
所得が高いほど税率が上がる累進課税の仕組みが、富裕層に多大な負担を課している。 - 富裕層の移住
高い税負担を避けるため、多くの富裕層がタックスヘイブン(租税回避地)に移住している現状がある。 - 税負担の集中化
富裕層が減少することで、残った富裕層にさらに負担が集中するか、低所得者層にも負担が拡大する可能性があると指摘されていました。
ドバイと日本の税負担の違い
授業では、富裕層がタックスヘイブンを選ぶ理由として、日本とドバイの税負担の比較が取り上げられました。たとえば、10億円を稼いだ場合、日本とドバイで残る資産の違いは以下のようになります。
| 地域 | 稼いだ額 | 税率 | 残る資産 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 10億円 | 最大80% | 2億円 |
| ドバイ | 10億円 | 5%以下 | 9.5億円以上 |
このように、ドバイのようなタックスヘイブンでは、稼いだ資産をほぼそのまま維持できることが富裕層の移住を促進しています。
- 国内消費の減少
富裕層が移住すると、その消費や投資が国内から失われ、経済が停滞する可能性があります。 - 税収の減少
富裕層が支払っていた税金が失われることで、社会全体の負担が増加します。
移住のメリットとデメリット
富裕層がタックスヘイブンに移住する背景には、確かに「税金を節約したい」というシンプルな理由があると思いますが、移住には多くのメリットとデメリットがありますよね。
移住のメリット
- 税負担の軽減 ドバイなどのタックスヘイブンでは所得税がほとんどかからないため、稼いだお金の多くをそのまま資産として残すことができます。例えば、日本で10億円を稼いだ場合、税金で80%が差し引かれ、手元に残るのは2億円ですが、ドバイでは約9.5億円がそのまま残ります。この差は非常に大きく、富裕層が移住を決断する大きな要因の一つ。
- 自由なライフスタイル タックスヘイブンは、税金だけでなく生活の質やビジネスチャンスの観点でも魅力的。たとえば、ドバイはインフラが整備され、治安が良く、世界中のビジネスリーダーと交流できる環境が整っています。そのため、新しい人脈を築きやすく、ビジネスを拡大するチャンスにも恵まれている。
- 柔軟なビジネス運営 法規制が比較的緩やかで、事業を立ち上げたり運営したりする際のハードルが低い場合が多い。さらに、多くの国際的な企業が集まるため、グローバルな視点での活動がしやすいのも特徴。
移住のデメリット
- 社会とのつながりの希薄化 富裕層が自国を離れることで、家族や友人と離れ離れになる場合があります。特に子どもの教育や親の介護など、生活に密接な問題に直面することも多く、移住には新たな課題が伴います。
- 文化や言語の壁 新しい国で生活を始める際、その国の文化や言語に適応する必要があります。特に言語が異なる環境では、日常生活やビジネスに支障が出ることも少なくありません。初めのうちは孤独感を覚える人も多いようです。
- 国内経済への影響 富裕層が国外に資産を移すことで、自国の経済が停滞する可能性があります。たとえば、日本国内では消費や投資が減り、地方経済や中小企業への影響が懸念されています。
竹花氏が指摘する格差社会が広がる理由
主に以下の3つに集約されるのかなと思いました。
1. 技術の進化による労働市場の変化
AIやロボットの進化により、単純作業や反復的な仕事が自動化されています。その結果、スキルを持たない労働者の仕事が減少し、高度なスキルを持つ一部の人に収入が集中するようになっている。
2. グローバル化と経済の偏り
グローバル化によって、多国籍企業や資本家が利益を拡大する一方で、中小企業や地域経済が取り残される傾向が強まっている為、安い労働力を求める流れで、低賃金の労働者の収入がさらに下がる状況も進んでいる。
3. 資本収益の偏り
「資本を持つ人はさらに富む」という資本主義の構造が、格差拡大を後押ししている。株や不動産といった資産を持たない人が、労働収入だけでは資産を増やしづらい状況に追い込まれることが原因。
竹花氏は、これらの要因が複合的に作用し、格差が広がる未来を指摘していると考えられます。
これからの社会に備えてできること
今回学んだことをもとに、「私たちにできること」をいくつか具体的に考えてみました。社会がどんどん変わる中で、これからどうしたらいいのか迷う人も多いと思いますが、まずは小さなことから始めてたいですね。
1. 仕事のスキルを磨く
これからは、「人にしかできないこと」がとても大切になる時代です。例えば、ただ決められたことをやるだけの仕事はAIに取って代わられる可能性が高いですが、「人と話して信頼を作る力」や「新しいものを作り出す力」は、まだまだ人が必要とされる分野です。仕事の中で自分がどんな役割を果たしているかを振り返り、「この部分をもっと伸ばしたら、必要とされる人になれるかも」と考えたいと思います。
2. お金のことを学ぶ
「税金」とか「投資」という言葉を聞くと難しそうに感じますが、実は基本だけなら意外とシンプルだとur-uの講義を聞いて思いました。貯金を銀行だけでなく投資信託などに回してみることなど、小さいことから始められます。「やったことないから不安」と思いますが、友人や家族で詳しい人に聞いたり、簡単な本を読んだりur-uで学び始めるのも一歩前進です。
3. 小さくても一歩を踏み出す
「何かしなきゃ」と思っても、何から始めたらいいか分からないことも多いですよね。そんなときは、「何でもいいから小さなことをやってみる」だけでも十分だと思います。たとえば、少しだけ早起きしてその時間を自分の勉強に当てるとか、お金の使い方を見直してみるとか。小さい一歩でも進んでみると、次に進むべき道が少しずつ見えてきます。私はここで学んだことをアウトプットしていきたと思います。